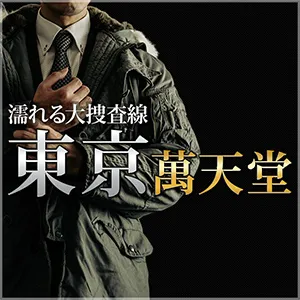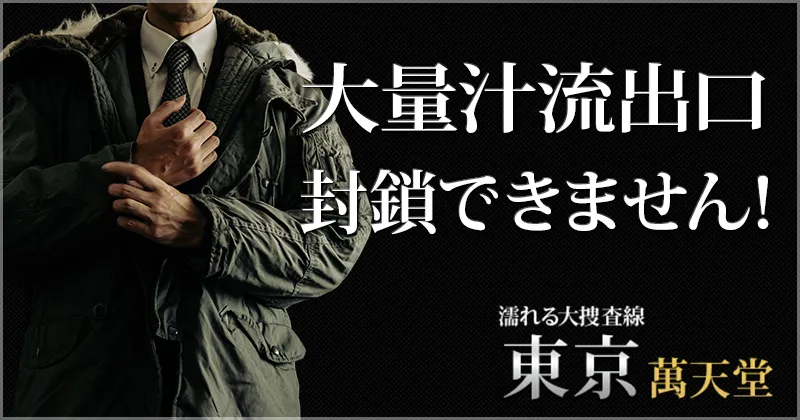
写メ日記
-
2024年10月26日 03:05 の投稿

「テクピになりたければガシマンせよ!」僕はテクピになるつもりはないので、やらないけど。昨日の日記を書いている時に思いついたのである。とても画期的で斬新な意見だ。今の時点では全く共感されないだろうが、まぁ説明を聞いてみようじゃないか。なかなかどうして、説得力のある説だと目から鱗が落ちるかもしれない。
僕はこの仕事をしていて常々感じているのは「女性は我慢してしまう」ということである。嫌なことがあっても、それを口に出して言うよりも、胸に秘めてストレスをため込んでしまう。ましてやそれが夜の事となると、まず間違いなく不満を相手に伝える事はしない。
口コミを見ればその傾向は顕著で、どれも10点満点ばかりである。だが実際にはそんなわけがないのだ。不平不満があっても、それを口コミに書く人は極端に少ない。吐き出すことによってストレスを解消するよりも、無かったことにして忘れてしまいたいと思う女性が多いのだ。
ガシマンをすることで10人中9人の人から「痛かった」「雑に扱われた」と不満を抱かれても、それを口コミに書かれることは滅多に無い。そして10人に1人は、「より強い刺激」を「より大きな快感」として受け取れる体質の女性がいるのだ。その人はきっと「今までで一番気持ち良かった」と感じ、絶賛する口コミを書くだろう。そうして100人の相手をすれば、10件のテクニックをべた褒めする口コミが蓄積される。一見するとまるでテクピのようではないか。その裏には90人の女性の不満があったとしても、口コミとして表面化することはほぼない。
夜の事に関して、負のフィードバックがほとんど行われないのは由々しき問題である。良かった時は褒められ、悪かった事については何も言われない。そのことを理解していないと、男側はどんどん勘違いしてしまうのだ。こうして謎にテクニックに自信を持つ男が蔓延っていくのである。
女性に話を聞くとセックスが上手い男なんてほとんどいないのに、世の中の男性の多くはそのことに無自覚で相変わらず勉強不足で、むしろ自分は上手いと自信を持っている。特にこの仕事をしている人は自信があるから始めたという人も多いだろう。だがその自信は、一部の女性の不満を蔑ろにして、相性の良かった女性からの誉め言葉を都合よく解釈しているだけなのかもしれない。
少なくとも僕は女性のことを知れば知るほど、「我慢してしまう」という性質への理解が深まり、負のフィードバックが無い事に対して危機感を覚えている。誉め言葉は素直に受け取るようにしている。だが「不満を言わない」=「不満が無い」というわけではないので、もしかしたら言えないだけで何か不満を抱えているかもしれないという思いは常に頭の片隅にチラついている。たぶん僕がテクニックに関して自信を持つことは今後も無いのだろう。
僕はありがたいことにたくさんの口コミを頂戴している。でも件数のわりに、性感に関する口コミが少ないように思う。それは「より大きな快感を与えること」よりも、「痛みや不満を与えないこと」を優先しているからなのかもしれない。僕は「当たり障りのないこと」が苦手でプロフや日記では好き勝手に書いているけれど、初回の性感については「当たり障りのないプレイ」から入ることが多い。何回か会って仲良くなったらその限りではないけれど。
ということで「テクピになりたければガシマンせよ!」という新説である。これは女性や女風への理解度が高い、なかなか興味深い意見ではないだろうか。僕はテクピになるつもりはないので、やりませんが。
ところで、飲み会で「俺、ドSだから笑」って言う人と仲良くなれたことがないんだけど、どうすればアイツらと仲良くなれるの?別に仲良くなる必要ない?それもそうね。


-
2024年10月25日 01:05 の投稿

たまには女風らしく性感に関する日記でも書いてみよう。
プレイ中に女性が言う「やめて!」にはいくつかの種類がある。やめて!(もっとして)やめて!(本当に一回やめて)どちらの「やめて!」なのかを正確に見極められる人が「上手い人」なのだろうか?
気持ち良い感覚がずっと続くのであれば、それはさぞ凄い快楽なのだろう。ましてや女性はM気質であると自覚している方が多いから、自らの意思に反してずっと快感が続くのであれば、より一層興奮するに違いない。そのため、「やめてって言われてもやめないよ?」みたいな少し強引なプレイに憧れを抱いている人は非常に多い。そしてそういった女性に刺さるように、「やめて!」と言われてもやめずに、気持ち良い状態をより長く継続させることが良い事だと思っている男性もたくさんいる印象だ。
僕の考えは少し違う。「やめて」と言われれば、基本的にはわりと素直に一回やめるようにしている。例によっていつもの逆張りではあるけれど、ちゃんと理由を文章化してみようではないか。
「やめて!の意味を見極められる人」=「上手い人」だとしよう。そこまではまぁ認めても良い。で問題なのは、それはちゃんと答え合わせしてるの?ってことだ。
「貴女はプレイ中にやめてと言いましたが、やめないでという意味だと私は解釈して続けました。正解ですか?」ってちゃんと聞いたの?「私はプレイ中にやめてと言いましたが、あれはやめないでという意味だったので、やめないで続けてくれて非常に気持ち良かったです」という言質は取れたの?もし仮に答え合わせができていたとして、女性側がそれを本音で言っているってどうやって判断するの?
僕はこの仕事をしていて、つくづく痛感するのは「女性は我慢してしまう」ということだ。特に夜の事となると、ネガティブな本音を話してくれることはほぼほぼないと思っている。それは口コミのページを見れば明らかだ。10点10点10点10点9点10点8点10点…って、そんなわけがないのである。実際には不満があったり嫌な思いをしていたとしても、女性はそれを我慢してしまうし、ましてや口コミに書いたりはしない。
「やめて!(やめないで)」と言われてやめなかった場合、女性はより大きな快感を得て男を褒めるだろう。「やめて!(本当にやめて)」と言われてやめなかった場合、女性はその不満を胸にしまって男には何も言わないだろう。男性側には、「やめてと言われてもやめないこと」に対する成功体験のみが蓄積され、「本当はやめて欲しかったのに」というネガティブなフィードバックは一切行われない。その結果が「やめてって言われてもやめないよ?」という自称ドSが爆誕するのではないだろうか。
少し踏み込んだ話をするならば、傾向として外イキした時の「やめて!」は本当にやめて欲しい場合が多い気がする。中イキの場合はそのまま連続してイケる人もいるので、やめないでと思っていることも多い。だが正直に白状するけれど、今イっているのが外なのか中なのかなんて僕には分からんのよ。イってる当の本人ですら分かってなかったりするのに、僕に分かるわけないじゃない。「分かる」と言う人もいるのだろうけれど、それもやっぱり答え合わせをする方法がないのだから、厳密には「分かっていると思っている」にすぎない。
僕は「やめて!」がどちらの意味か、常に正しく判断することは不可能だと思っている。やめないことによって得られる男性にとって都合の良い成功体験よりも、「本当はやめて欲しかったのに」という女性の不満を無視するリスクを回避したい。なので「やめて!」と言われれば一旦様子を見ることが多い。より高い最高点数を目指すより、最低点数を引き上げてアベレージを高めたい。その結果として一部の人からは物足りないと思われたとしても、誰に対しても「不快な思いをさせないこと」を最優先したいのだ。
僕は日記やプロフは「刺さる人に刺され!」って思って書いてる。でも性感については「広く浅く多くの人にそれなりの満足を」ってスタンス。「やめて(本当にやめて)って言われてもやめないよ」という憐れな勘違いテクニシャンになるリスクを完全に排除できないので、やめてと言われたらやめる。僕は別にテクニシャンになれなくていい。あ、でも回数を重ねて信頼関係ができればその限りではないよ。
また長々と面倒臭い日記を書きやがって!目障りだからやめて(本当にやめて)だって!?やめてって言われてもやめないよ?


-
2024年10月23日 01:05 の投稿

焼き鳥はタレ派ですか?塩派ですか?そんな問いかけは不毛だ!「場合による」「気分による」としか言いようがない。
白米があるならば、タレが良いかもしれない。飲み物によっては塩が良い時もある。そういうものではないだろうか。
サディストか、マゾヒストか。これも「その時の気分による」「相手次第」である。僕はほとんどの人が両方の性質を持ったスイッチャーだと思っている。SにせよMにせよ、本当にどちらかに偏った人は実際にはかなり少ない気がする。自己申告のSだのMだのというのは、Sだと思われたいMだと思われたいという意思表示の場合が多い。
僕はかつて高所恐怖症を自称していたが、自分で言うのを辞めたら高所恐怖症も無くなった。人は演じる生き物だ。与えられた役割を内面化してしまう。つまりSであると言う事によって、その発言との整合性を取る為にSな自分を演じてしまうのである。
Sが主導権を握っている格上でMはそれに従う存在というイメージがあるから、だいたいの男はSであろうとする。だが実際にSであるかどうかは重要ではなく、Sというラベリングを自己成就させているケースは多い。
本当にSならば良いのだが、自称Sの中には自分本位のワガママな振る舞いを「サディスト」という言葉で正当化するタイプの人もいる。逆に全てを人任せにして受動的であることをMと称する人もいる。それはちょっと違う気がする。
自己申告のラベリングでキャラを固めるのも良いけれど、それによって選択肢を狭めているとすれば勿体ない。そしてこれらのラベリングは「平凡」への反抗であり、「個性」への盲目的な憧れを秘めている。だが実はその「個性」への羨望こそ、他ならぬ「平凡」の証明だったりする。かつて僕は「誰よりも無個性な人間になりたい」という歪んだ願望を抱き、だがその考え方こそ他ならぬ「個性」であるという事実に打ちのめされたことがある。
そんな僕が珍しく自らにラベリングしたのが「ひねくれ者」である。ひねくれ者であることに憑りつかれていると感じる時もある。正直、自分でも面倒臭いを思う時もある。ひねくれ者であるが故にひねくれ者であることからもひねくれて、ひねくれ者でないふりをする。でもそれをこうして文章化することによってそこからもひねくれなければならない。そうして僕は結局ひねくれ者を自称する。もはや自分でも思考の到達点が迷子で、訳がわからない。
ちなみに僕は味に対するこだわりがあまりないので、食感が独特な食べ物が好きかも。焼き鳥だと砂肝とか鳥皮が好き。むね肉もも肉の違いはあまり分かっていない。

-
2024年10月20日 02:05 の投稿
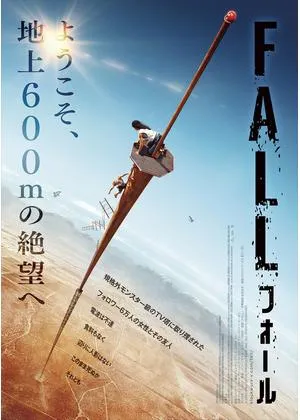
皆さんは高い所はお好きですか?僕は元々高所恐怖症を自称していたのですが、途中で辞めました。辞めようと思って辞められるものなのか?と思われるかもしれませんが、病院で診断を受けた正式な恐怖症でないのであれば、辞められると思います。
僕は小学5年生の時に学校の行事で東京タワーに行ったのですが、思いのほか自分以外にも自称・高所恐怖症が多いことになんか萎えちゃったんですよね。ひねくれ者としては、皆が同じことをしていると冷めるというか。所詮ほとんどの高所恐怖症って自己申告でしかないし、言ったもん勝ちだよなぁって思ってしまったのです。そして二度と高所恐怖症とは言わなくなったのですが、するとどうでしょう。不思議なことに高い所への苦手意識はなくなったのです。ひねくれ者の矜持によって、高所への恐怖を克服しました。そういうものです。
「恐怖」とは「死ぬことに対する警鐘」です。人間は空を飛べず肉体も脆弱なので、高所から落ちたら死にます。落ちたら死ぬ高さに対して恐怖を感じるのは生物として当たり前のことなのです。それを高所恐怖症と自称して怖さとして認識するか、本能的に普通の事としてスリルと解釈するか。本人の意識によってコントロールできることなのかもしれません。
そんなわけで僕は高所恐怖症というわけではないのですが…。高い=怖いという人間の本能に刷り込まれた恐怖を久しぶりに思い出させてくれた映画を紹介します。「FALL/フォール」という作品です。Amazon Prime Videoで配信中。
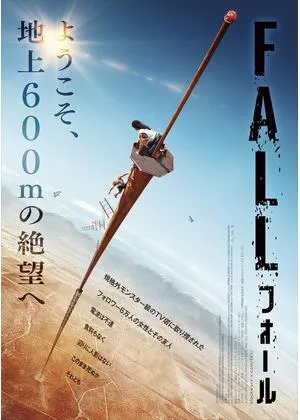
山でのフリークライミング中に夫を落下事故でなくしたベッキーは1年がたった現在も悲しみから立ち直れずにいた。親友ハンターはそんな彼女を元気づけようと新たなクライミング計画を立てて現在は使用されていない超高層テレビ塔に登ることに。老朽化して不安定になった梯子を登り、地上600メートルの頂上へ到達することに成功。しかし梯子が突然崩れ落ち、2人は鉄塔の先端に取り残されてしまう…。
2人の女性が地上600メートルの細い塔の上に取り残された!!塔の上は電波も届かず救助は呼べない。食料もない。さぁどうする!?というワンシチュエーション物のサバイバルスリラー。高所恐怖症発狂必至映画。
塔の上に取り残されたは良いけれど、そこから映画としてどうするのか。ワンシチュエーション物は「変わり映えしない画」という問題を抱えているが、その「変わり映えしない画」が地上600メートルなので恐怖そのものなのである。話を展開させ難いシチュエーションではあるが、想定しうる最悪の展開は一通り全て起きるので最後までスリリングだ。
主人公の親友であるハンターは近年の映画でよく見かけるSNS中毒でフォロワーを増やすことに必死なパリピ系の女性。だがこの手のキャラが酷い目にあって「ざまぁみろ!」っていう映画ではないのが驚き。正直、いけ好かないインフルエンサーを最悪なシチュエーションで苛め抜いてニヤニヤするタイプの映画だと思ってた。「状況を悪くさせる為の舞台装置として配置されたビッチ」と言うキャラは映画でよく見るけれど、ハンターは意外とそうではないのが新鮮。…まぁビッチではあったけど。パリピ系キャラは「こんなアホどうでもええわ」となりがちだけど、ちゃんとした行動原理があるので不快感が少なく素直に応援できるキャラ。むしろ状況に流されるだけでいつまでもウジウジしている主人公の方がイライラするかも。ただそんな主人公もずっとそのままというわけではなく、危機的な状況に立ち向かう中で過去と向き合い、人間的な成長を描くしっかりした脚本になっているのが憎たらしい。
もっと頭空っぽなパッパラパーB級映画だと思ってたのに!普通に面白い映画じゃないか!
ただ終盤にちょっとした「捻り」があるんだけど…。ぶっちゃけそれは想定の範囲内。まぁまぁ映画を観ている人ならこの「仕掛け」は真っ先に思い浮かぶんじゃないかな。「どんでん返し」って演出でもないから、展開が読まれることも想定した上での脚本なんだろうけど。
ラストはちょっと盛り上がりにかけるかな。僕は映画を観ている時に生意気にも「僕ならこういう展開にする!」とか考えながら観ちゃうんだけど、正直ラストに関しては僕の妄想展開の方が面白い自信がある笑妄想展開を書いた質問箱をXに投稿しているから、この作品を観たことがある人やネタバレを気にしない人は見て。絶対こっちの方が面白くない?【東京/千葉萬天堂】あきら Xアカウント
とはいえ高所恐怖症の人にこそ見て欲しいオススメの映画です。
そういえばジェットコースターが落下する際の無重力感に恐怖を感じて股間が縮み上がる感覚のことを「タマヒュン」と表現するけれど、女性の場合はどういう感覚なのだろうか?

-
2024年10月14日 02:05 の投稿
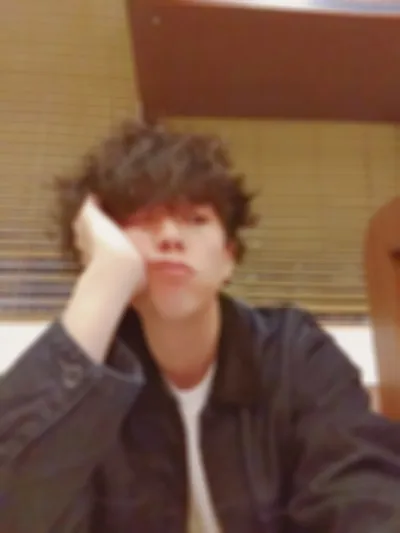
プロレスが好きで「プロレスとは何か?」を考えすぎた結果、近代プロレスを受け入れることができなくなってしまってプロレスファンを辞めた一番面倒くさいタイプの元プロレスファンから観た「極悪女王」の話。あまりにも面白過ぎて色々と語りたい欲が止められない!元プロレスファン的にどうしても紹介しておきたかったことがたくさんあるのだ!
いきなりだが、プロレスとは事前に勝ち負けを決めた上で行われるエンターテイメントショーである。そして試合の段取りや勝敗に関する決め事を「ブック」と称する。これはあくまでも隠語であり、日本のプロレスにおいて「ブック」はとても曖昧な存在だ。ファンも「プロレスとはそういうもの」と理解しながらも、そこには触れないように見て見ぬふりをして楽しむ人が多い。
プロレスを題材としたドラマを制作する際に「ブック」の存在について触れるかどうかは大きな問題だ。そして「極悪女王」が画期的だったのは、作中ではっきりと「ブック」に言及している点である。勇気のいる選択だったと思うが、今現在のエンタメ化を極めたプロレス界においては、もはやそこに配慮しなくても大丈夫という判断なのだろう。僕もそれを倣って、「ブック」ありきで話そうではないか。
逆にブック無しで、勝ち負けを決めずに行われる真剣勝負のことを「ガチンコ」という。今となっては「ガチ」という言葉はすっかり世間に浸透したが、もともとはプロレスや大相撲の隠語なのだ。
プロレスでガチはご法度である。結果を決めずに試合を行えば、「客を楽しませる為の試合」ではなく「自分が勝つ為の試合」となってしまう。そうなれば見ている人は楽しくないし、何よりもどちらかの選手が怪我をしてしまう確率が飛躍的に高くなる。年間に200試合以上するプロレスにとって、怪我で試合に出られなくなることは何よりも避けたいのだ。
だが頻繁にガチの試合が行われていた頭の狂ったプロレス団体があった。それこそ「極悪女王」の舞台となった80年代の全日本女子プロレス、通称「全女」だ。全女ではガチのことを「ピストル」と呼んでいた。とはいってもピストルは完全なるガチではないのが難しいところ。
プロレスとは相手選手の両肩をマットにつけた状態で3秒間抑え込めば勝ちである。逆に抑え込まれた側は、3秒以内に肩を上げようと抵抗する。だがプロレスは勝敗が決まっているショーなので、基本的には「抑え込むフリ」でしかない。
ピストルとは、この「抑え込み」を本気で行う試合形式なのだ。序盤は「普通のプロレスの試合」として行われ、決まった時間が経過したらピストルが開始される。後輩レスラーが適当な技を出して相手を仰向けにして「本気で」抑え込む。3秒以内に返すことができれば、攻守交替。こうして決着がつくまで交互に技をかけあうのがピストルである。真剣勝負とは言っても、首から上を攻撃したり、受身の取れない技を出していいわけではない。
そして全女特有の暗黙のルールはピストルだけではない。それが「25歳定年制」である。どれだけ人気があっても25歳を迎えると会社からの扱いが露骨に悪くなり、ほとんどの選手は25歳を過ぎるとほどなくして引退してしまうのだ。当時はまだ転職や女性の社会進出に対する理解が進んでいなかったので、早めに女子プロレスから足を洗わせることで第二の人生設計を立てやすいという意図があった。
この「25歳定年制」と「ピストル」の存在は作中では描かれなかったが、知っていると「極悪女王」の素晴らしいストーリーをより深く楽しめると思う。
例えば作中においては「ジャッキー佐藤vsジャガー横田」がブック無しで行われていた。これは実際にピストルだったと言われている。ジャガーが勝ち、王座を失ったジャッキーはこの後すぐに引退してしまう。この時のジャッキー佐藤は24歳。25歳定年制があるため、どの道レスラー生活は長くなかったのだ。そう考えると「わざと」負けたわけではないのだろうが、どうせもう辞めるのだから後輩に花を持たせてもいいかと思っていたのかもしれない。
あるいは物語のクライマックスである「長与千種vsダンプ松本」の敗者髪切りマッチ。作中では長与が「今の全女人気は全部自分のおかげ」という傲慢なキャラになっており、勝ちブックを譲るように直談判するもブック無しで戦う事になるという展開だった。これはドラマオリジナルのフィクションだと思う。実際の長与はある意味で究極のエゴイストであり、自己プロデュース能力が異常に高かった。自分が結果的に美味しくなるのであれば、負けることも公衆の面前で丸坊主にされる辱めも、喜んで受けるタイプだ。なのであの試合はブックが有ったし、長与は自ら進んで負けを受け入れたと思う。長与本人がドラマの監修に入っているのにこの描写をNGにしなかったのも、「こうした方が面白い」という計算が出来る人だからなのだろう。
プロレスに否定的な人や興味が無い人はブックについて冷ややかな意見を述べる。「プロレスってやらせじゃん笑」と。では勝ち負けが事前に決まっていると言うけれど、それは誰がどうやって決めているのだろうか?
人気のある選手が勝つのか、実力のある(ピストルが強い)選手が勝つのか。これはプロレス業界が抱える命題であり、「極悪女王」の中でもその葛藤は描かれていた。アイドル的な人気を博したジャッキー佐藤がエースの時は全女は大ブームを巻き起こした。だが歌って踊って人気になったアイドルが「プロレスラー」としてエースであることに否定的な意見もあるだろう。一方でピストルは強いが華の無かったジャガー横田がエースだった時代は、人気が低迷した。どれだけ実力があっても、客が呼べなければ会社としてやっていけないのだ。
そう考えると、人気の長与と実力の飛鳥がクラッシュギャルズとしてブレイクするも、方向性が違ってギクシャクしていく展開もより解像度が上がって見えるのではないだろうか。
25歳というタイムリミットに追われながら、「人気があればそれでいいのか?」「実力でのし上がるのが正解なのか?」と各々のイデオロギーをぶつけ合う事でブックを超えたドラマが生まれる。プロレスとはショーであり、多くの部分がフェイクだ。だがそこに込められた人間関係や感情には、何よりも純粋なリアルがある。プロレスとはゴールの無いマラソンであり、まるで底が丸見えの底無し沼だ。
僕が好きだったプロレスはこういうのなんだよなぁ…と「極悪女王」を観て懐かしい気持ちになった。過激なセンチメンタリズムに浸る秋の夜長。
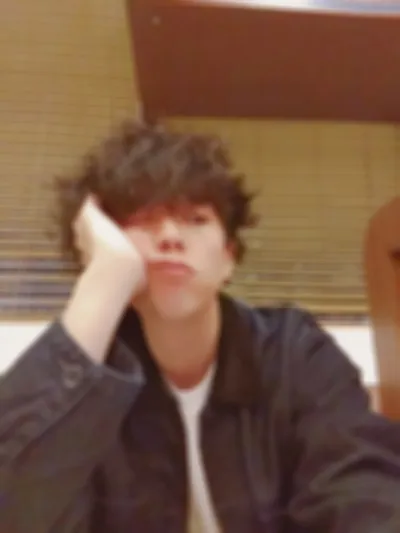
深夜のジョナサンで不貞腐れてる人。